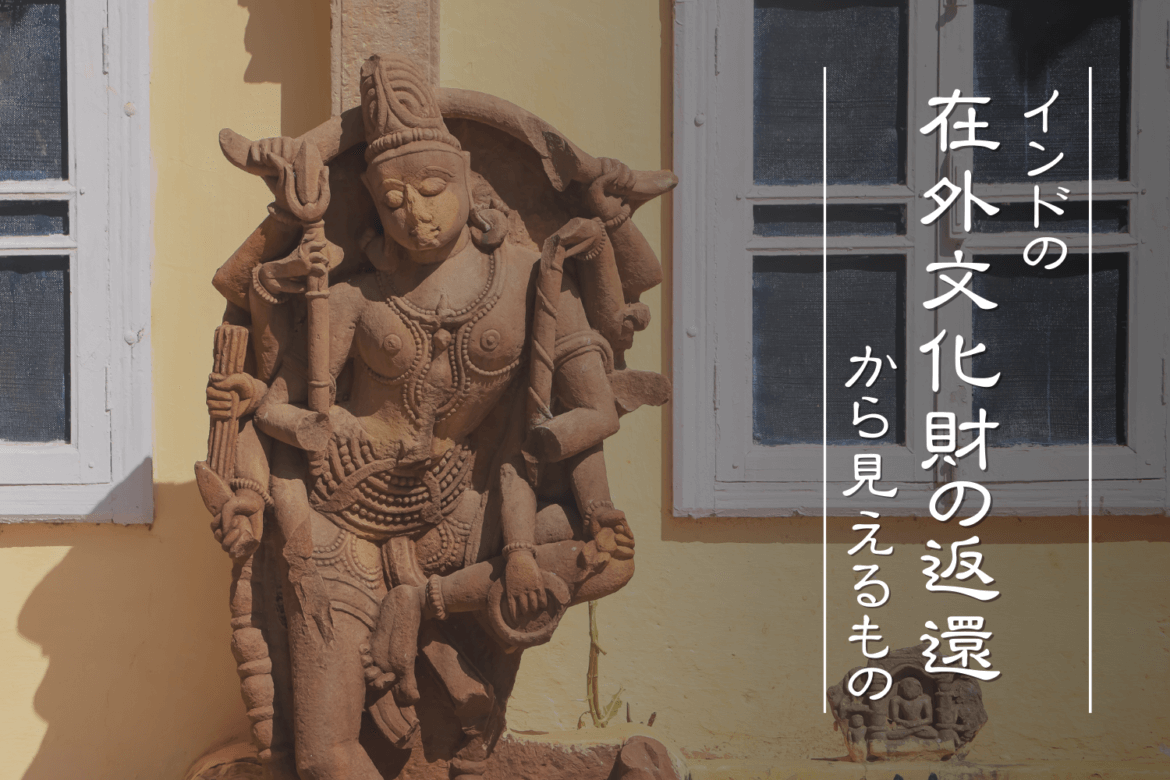2024年9月25日のCNNの報道によると、米国のジョー・バイデン大統領はアメリカが保有するインド起源の文化財約300点を返還したと発表した。同時期に開催されたQUADの米印首脳会合と時期を合わせ、ナレンドラ・モディ首相とバイデン大統領は文化財を前に記念撮影を行った。日本のマスメディアは詳細について報じておらず、あまり重要な出来事としては認識されていない。しかし、この件はインドが大国の仲間入りをしたことを反映する画期的な出来事である。そこで本稿では、アメリカによるインドの在外文化財の返還は、戦前の日本における不平等条約の改正に比する重要な出来事であったことを明らかにする。
まず、文化財はその国で歴史的に制作されてきたものであり、その国の国民の共有財産であるという現代の考えは、近代における私的所有権の発達と関係がある。帝国主義時代において、国家を一種の企業と見なす傾向が強まり、個人に認められる私的所有権を法人たる国家も有しているとの見解に発展した。この理屈においては、インドの文化財はインド国民のものであるが、当時は人種差別が横行していたので、白人と同じ権利は有色人種には認められておらず、奴隷制度などはその最たるものである。これは国家間の関係で言うと、宗主国と植民地と言い換えることができ、インドの文化財はインドを侵略していたイギリスを初めとするヨーロッパ諸国の所有物とみなされた。これには他にも一見合理的とも思われる主張もある。例えば、仏教壁画の宝庫として知られる敦煌莫高窟は、ドイツ人の探検家シュタインによって多くの仏画が剥がされ、本国に持ち帰られた。シュタインにとっては自分の名声を高めることも理由の一つであったが、人類共通の遺産を保存技術や環境がより整っている欧米で保管することは、文化財収奪をめぐる大義名分として大々的に謳われていた。このように植民地支配を正当化する論理の一端として、文化財収奪も位置付けられるのである。
現代においては、人種差別撤廃条約が履行されているように、文化財に関しても返還する流れが起きつつある。しかし、文化財返還に抵抗するイデオロギーも確かに存在しており、旧宗主国と旧植民地という力関係だけではなく、一見合理的に思われる主張もある。例えば、イギリスの大英博物館は帝国主義時代には世界各国から集めた収蔵品が所狭しと陳列され、収蔵庫にはさらに多くの膨大な資料が保管されている。かつて存在していた大英帝国の縮図のような場所と言えるが、文化財返還に抵抗する論調では、一か所に世界の文化財が集められていれば、現地まで見に行かなくてもよく、便利であると主張される。国際法で認められている国家の所有権よりも経済合理性などの功利主義を優先する思想であり、初見では納得できる部分もあるが、よくよく考えてみると極めて自己中心的な発想であることがわかる。実際には、このようなイデオロギーに基づいて、旧宗主国から旧植民地への文化財の返還は遅々として進まない状況であった。
そのような中で、今回はアメリカという世界で最も強大な軍事力を持つ国家が、インドというおそらく最も文化財収奪の被害を受けてきた国家に対して、その文化財を返還することが決まったのである。少し話が逸れるが、戦前の日本も西洋列強と不平等条約を結ばされ、労働者が必死に生産した生糸などが極めて低い値段で買いたたかれ続けた。これには当時の江戸幕府が関税の概念を正しく理解していなかったことが原因の一つであるが、不平等条約が改正されたのは1904年の日露戦争で勝利した後であり、半世紀に及ぶ不断の努力が求められた。インド外務省によれば、バイデン大統領との首脳会談でモディ首相は「インドの歴史的な物質的文化の一部であるだけでなく、インドの文化と意識の内核を形成している」と発言したとされている。このようにインドにとって文化財の返還とは、建国以来の悲願であったことがわかる。
以上のように、インドの在外文化財がアメリカから返還されるという出来事は、インドが大国として認められたことを示している。インドの人口は2023年に中国を超えて世界一となった。同年にはドルベースの名目GDPで旧宗主国のイギリスを抑えて世界5位となり、2025年には日本とドイツを抜いてアメリカ、中国に次ぐ世界第3位となると予想されている。インドはアメリカ、オーストラリア、日本とともにQUADの構成国であり、インド太平洋における日本の安全保障上の重要なパートナーでもある。自他共に認めるグローバルサウスの代表格としてもインドの影響力は今後も高まる一方であると言えよう。
インドの在外文化財の返還から見えるもの
previous post