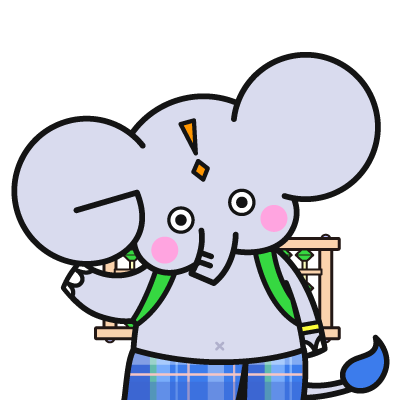宗教、貧富の差、カースト、あるようでないルール、地域によって異なる食事や言語など……挙げればきりがありません。
本記事では「多様性の国インド」を、宗教や伝統文化の視点から深掘りしてみました。

そして、宗教や文化からたどり着くインドの「他人を許す心」や「度量の広さ」について。
堅苦しくなく、日常生活やダンス、映画から学べるインドの多様性について見ていきましょう。
多くの宗教が入り混じる多様性の国インド
|
割合で見てしまうとイスラム教は少なく感じるかもしれませんが、人口で見るとどうでしょう。
インドの人口が約13億人として、
|
約13%のイスラム教でも、日本の人口の2倍近くの人々が信仰しているのです。

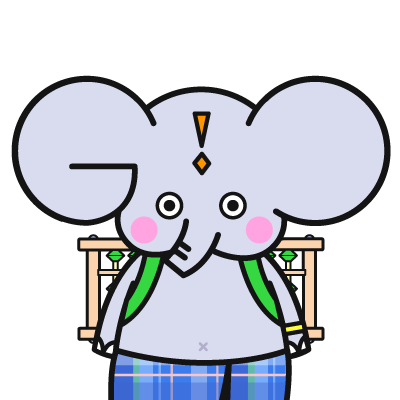
ヒンドゥー教は、日本でも有名なガネーシャやシヴァなど多くの神様がいる多神教です。
インド人は、それぞれにお気に入りの「推し神様」がいるそう。牛が神聖な動物のため、原則、牛肉は食べません。
一方、イスラム教は偶像崇拝をせず、1日5回の礼拝があり、豚肉を食べることを禁じています。
インドでは、ヒンドゥー寺院、イスラム教のモスク、シーク教寺院などが近くに並んで建っていることも珍しくありません。もちろん異なる宗教の人々も、入り混じりながら生活しています。

でも、インドを見るとどうでしょう。別々の宗教が並んで一緒に暮らしています。
ヒンドゥー教徒、イスラム教徒が共存したオフィス

約50人が働くオフィスの中で、一人だけイスラム教徒の人がいました。
イスラム教徒にとって金曜日は特別な日で、モスクで礼拝をします。イスラム教徒の彼も、長めの昼休みを取って、オフィスの近くにあるモスクに行っていました。
彼が金曜日に礼拝に行くのは周知のことで、誰も特別視はしません。
一方、オフィスで多くを占めていたヒンドゥー教の同僚たちは、毎週決まった曜日にサルの神様「ハヌマーン」のお寺に行っていました。
ヒンドゥー教のお寺に行くと「プラサード」というお供え物のお菓子がもらえます。

このように、1つのオフィスにヒンドゥー教徒、イスラム教徒が存在しても、それぞれ自分たちの信仰をして誰も特別視しない。ただ、普通に共存していました。
それどころか、ヒンドゥー教徒の同僚たちがイスラム教徒の同僚に対して「こいつはパキスタンなんだよ」と冗談でしょっちゅう言っていて、私の方がひやひやしたものです。(パキスタンはイスラム教が大半を占める国で、紛争も起こしています。)

異なる宗教も認め、共存するインドに多様性の一端を見たのです。
ヒンドゥーとイスラムの融合「カタックダンス」

インドには「8大古典舞踊」と呼ばれる舞踊が存在し、その1つがカタックダンスです。
|

イスラム様式の宮廷でカタックダンスが踊られている様子は、映画「Bajirao Mastani」の中でも見ることができます。
インドで絶大な人気を誇るDeepika Padukone(ディーピカ・パードゥコーン)が、美しくカタックダンスを踊っています。
振付は、現代カタックダンスの様式を築いたと言われる、インドの人間国宝Pandit Birju Maharaj(パンディット・ビルジュ・マハラジ)によるもの。
カタックダンスは衣装にも「ヒンドゥースタイル」「ムスリム(イスラム)スタイル」があったり、あいさつの仕方がそれぞれの宗教で異なったりします。

逆に、ヒンドゥー教徒のダンサーがムスリムスタイルの衣装を着て踊ることもあります。
現代は「カタックダンスとはこういうもの」として、宗教のことをあまり気にしない、もしくはそこまでわかっていないインド人も増えてきたそうです。
しかし、ヒンドゥーとイスラムの融合が見られるカタックダンスは、文化的にとても興味深いと思います。
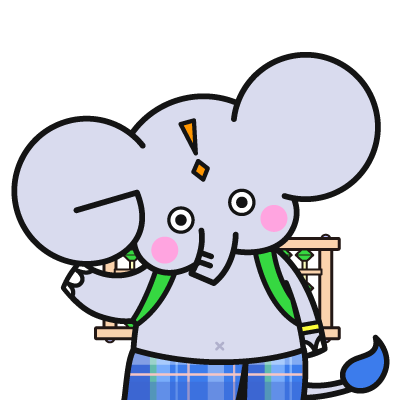
インドの社会問題や宗教について切り込んだ映画「PK」

日本ではタブー視されがちな「宗教」ですが、インドにはその宗教を積極的に題材にした映画があります。
映画「PK」
宇宙からきた主人公「PK」が「神様って何?」「宗教って何?」と、純粋な視点でインドの宗教、文化に切り込んでいきます。

また、男女の恋愛物語も同時に進んでいきます。熱心なヒンドゥー教徒の家に生まれた女性と、イスラム教徒の男性の恋物語で、その中でも宗教についての葛藤が描かれます。

インド映画お馴染みのコメディーあり、恋愛あり、涙ありで、インドを知っている人も、知らない人も、すべての人におすすめの映画です!
異なるものを受け入れ、許す心を持つインド

今まで述べたように、インドではいろんな宗教の人が混ざりあって暮らしています。
多宗教が混ざりあって存在できる要因の1つが、インドの「異なるものを受け入れる心」だと思います。自分とは違う宗教や考え方の人を認められなかったら、共存するのは難しいですよね。

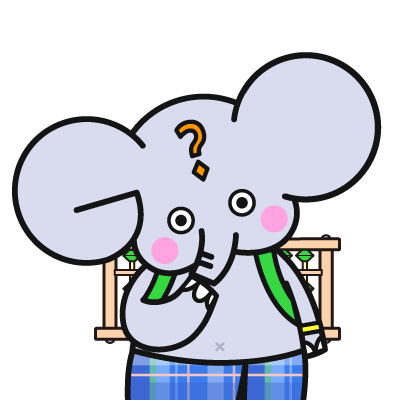
日本では「他人に迷惑をかけてはいけません」と教えますが、インドでは「他人に迷惑をかけて生きているのだから、人のことも許してあげなさい」と教えます。
ここに、インドの「他を許容する心」のすべてが現れているような気がします。
日本人の私たちからすると、インドは日本とは違い、上手くいかないことも沢山あるように感じるかと思います。
何もかもスムーズにいかないし、自分とは違う考え、違う宗教の人も多い。そんな中で、「違うこと」にいちいち目くじらを立てて、衝突していたら疲れてしまいますよね。
だからこそ、インドでは他を認める許容力が育まれたのかな、とも思います。

私はインドの「許容力」に、日本人が学べることが大いにある気がしています。インド人に、心穏やかに生きるヒントをもらいましょう。